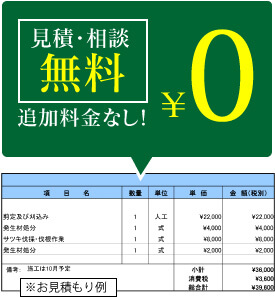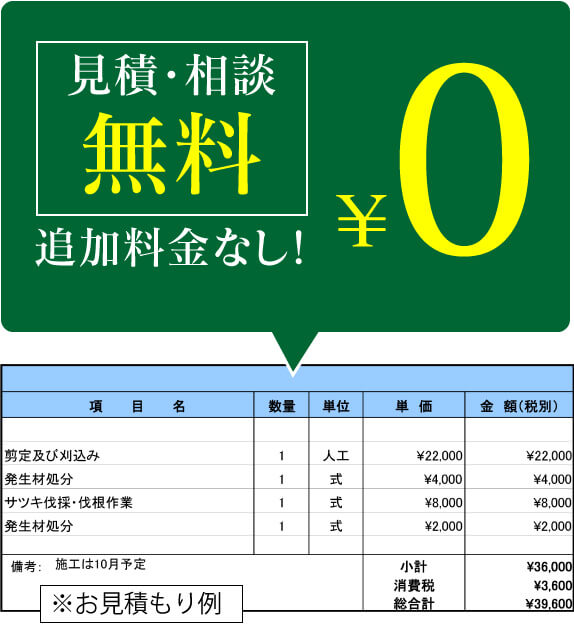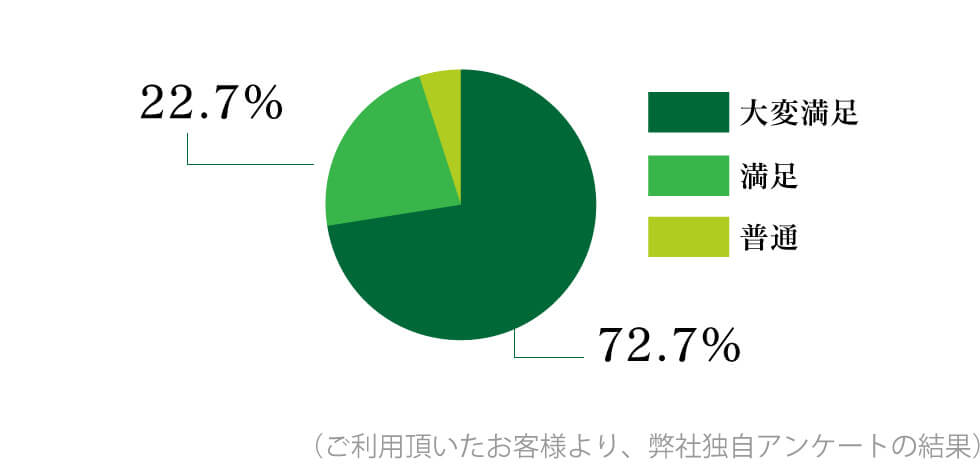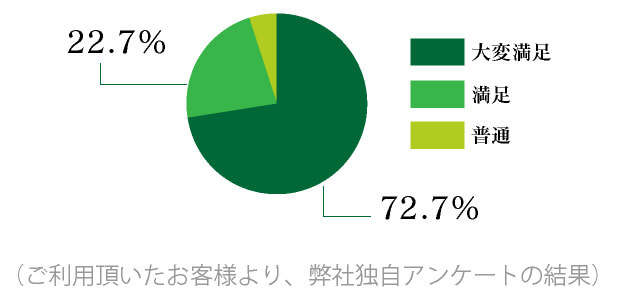花壇の草花や鉢づくりの植物に肥料が必要なように、庭木の場合も肥料を与えなければなりません。しかし、与える時期を間違えたり、肥料の成分も知らずにたくさん与えすぎたのでは、かっえって害になりますから、基本的な知識は身につけておく必要があります。このページでは、庭木や花木への肥料の与え方をプロの庭師が解説致します。
庭木が美しく育つ四大肥料

庭木の生育に欠くことができない栄養素が、窒素(N)、リン酸(P)、カリ(K)、カルシウム(Ca)の四要素で、四大肥料と呼ばれています。これらの栄養素は庭木が育つ過程でたくさん消費されます。また、土中に常に留まるわけではなく、雨水によって流出することが多いため、施肥で不足分を補う必要があります。
窒素(N)
窒素は茎の生育を盛んにしてくれる肥料です。肥料の成分にはそれぞれの特徴があって独特な働きをしています。窒素の場合は、一名”葉肥え”とも呼ばれるように、葉に葉緑素を作り、いきいきとした枝葉を伸ばすという働きをしています。この成分が不足すると、葉は黄色くなって生気を失ってきます。
リン酸(P)
木が若いうちは根の発達を促進させ、成木になると細胞分裂を盛んにする働きをするのがリン酸です。美しい花を咲かせたり、実をたくさん付けるのに欠かせない肥料なので、”実肥え”とも呼ばれます。
カリ(K)
しっかりした根を張らせるために必要な成分です。一名を”根肥え”とか”茎肥え”というように、根や茎を強くし、冬の寒さに耐える力を蓄えたり、病気に対する抵抗力を高める働きがあります。これらの成分は単独で働いているわけではなく、お互いに作用しながらそれぞれの役目を果たしているのです。
カルシウム(Ca)
カルシウム(Ca)を含む肥料の総称を「石灰質肥料」といいますが、石灰質肥料は、病害虫に対する抵抗力をつける働きと、根の生育を促進する働きがあります。そして、土壌酸度の調整にも必要な要素で、植物の生育に重要な役割を担っています。
肥料の種類と特徴

肥料には、有機質肥料と無機質肥料があります。
有機質肥料は、有機物を原料とした肥料で、植物質肥料と動物質肥料があり、動植物の死骸や排泄物などを原料にした天然肥料です。土中の微生物が有機物を分解した栄養素を植物が吸収し、ゆっくりと長く効果を発揮する緩効性の肥料です。
無機質肥料は、鉱石などを化学合成させた肥料で、 要素を1成分しか含まないものを単質肥料(リン酸肥料・窒素肥料など)、要素を2成分以上含むものを複合肥料といいます。無機質肥料は、水に溶けやすく、無臭で、速効性があるので、とても扱いやすい肥料です。
| 種類 | 成分 | 速効性 緩効性 | 特徴 | |||
| 窒素 (N) | リン酸(P) | カリ (K) | ||||
| 無機質 | 化成肥料 | 化成肥料は、「NPK比」と呼ばれる、「8-10-5」と3つの数字が書かれた表記が、窒素(N)が8%、リン酸(P)が10%、カリ(K)が5%、含まれているということです。 NPK比は、枝葉にはNが多いものを、花実にはPが多いものを、根や茎にはKが多いものを与えましょう。化成肥料には、無機質と有機質の両方の成分を含むものや、速効性や緩効性のどちらの種類の肥料も開発されていますので、その庭木に適したものを選びましょう。 | ||||
| 有機質 | 油かす | 5 | 2 | 1 | 緩効性 | 窒素の割合が多い |
| 鶏ふん | 3 | 6 | 4 | 緩効性 | 鶏ふんは堆肥に混ぜると効果的 | |
| 骨紛 | 4 | 20 | 0 | 緩効性 | 主にリン酸を含む | |
| 草木灰 | 0 | 3 | 8 | 緩効性 | 土壌を中和し、カリ肥効がある | |
| 堆肥 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 緩効性 | 通気、保水性を改善し土壌改良する | |
肥料の与え方
| 元肥 (基肥/もとひ) | 庭木を植える時に植穴の底に施す肥料です。元肥には、緩効性肥料を根と肥料が直接接触しないように、元肥の上に土を持って植え付けます。 |
|---|---|
| お礼肥(おれいごえ) | 花が終わった後や果実を収穫した後に、樹勢を回復させる為に与える肥料で、お礼肥と呼ばれ、速効性肥料を与えます。 |
| 追肥(ついひ) | 対象の庭木の適期に、追加で施す肥料です。 |
| 寒肥(かんごえ) | 春の庭木の生育が旺盛な時期に効き目が現れる様に、冬の間に与える肥料のことで、緩効性肥料を施します。 |
| 芽だし肥 (春肥/めだしごえ) | 春の萌芽期に施す肥料で、萌芽、枝の伸長を促進するために与える速効性肥料。 |
| 秋肥(あきごえ) | 秋に季節が変わる頃に、越冬する体力をつけるために施す肥料。 |
| 置肥(おきごえ) | 鉢植えの、鉢の回りに置いて水やりの際に肥料の栄養素が溶け出すように施す肥料。 |
| 水肥(みずごえ) | 水やり代わりに施す液体肥料で、速効的な効き目を必要とする際に与えます。 |
施肥の方法
植えたばかりの木には肥料は与えない
新たに植えた苗木が移植したばかりの木には、肥料は与えないようにしましょう。根の先端を切って、枝葉を少なくするために、切られている木は大きなダメージを負っていますから、肥料を与えても正常に吸収できる状態ではなく、逆に肥料負けして根を痛めてします危険性もあります。肥料を与えるのは、木が根づいて根毛が出てからですから、ひと冬かひと夏越してから与えるようにしましょう。
肥料は根元には与えない
肥料を吸収するのは、太い根ではなく、根の先にある根毛ですから、根毛のある位置に肥料は施さないと吸収できません。なお、土の中の水分は根毛の細胞液より濃度が低く、吸収されやすくなっていますが、希釈濃度が濃い水などの場合は、根の細胞液が奪われ、肥料負けとなってしまうため、希釈は適正に行いましょう。
寒肥は掘って埋める
寒肥は、春になって木の成長期での栄養の元となるものですが、樹種によっては冬の間にも活動を行っているものもあるので、樹種を調べて施すようにしましょう。
寒肥は、樹冠の少し内側に掘って埋めましょう。このことで根の先を切って埋めることになるので、春の徒長枝を抑える効果もあります。
花木には必ずお礼肥を与えよう
木々が花を咲かせるのは、大変な体力を使うらしいですから、花や実を付けた後には、必ずお礼肥を与えておきましょう。お礼肥は、木の疲労回復剤となるもので、できるだけ早く樹勢を回復させて、来年の花や実の養分を蓄えさせてあげましょう。
生垣にも肥料を与えましょう
主木や花木、果実が実る木には肥料を忘れず施すけれども、良く忘れられるのが生垣です。生垣は悪条件の環境に植えられていることが多いので、忘れずに与えておきましょう。
施肥の場所
環状施肥(かんじょうせひ)
対象の木の周りに、深さ20㎝~30㎝の溝を掘り、その溝に肥料を施します。溝の位置は葉先の下を目安に掘りましょう。
壺状施肥(つぼじょうせひ)
対象の木の周りに、深さ30㎝~40㎝の穴を掘り、その穴に肥料を埋める方法です。木と木の間隔が狭い場所や生垣などの際に行う方法です。
放射状施肥(ほうしゃせんじょうせひ)
対象の木の根と根の間に沿うように、木から放射状に溝を掘って、肥料を埋めます。
全面施肥(ぜんめんせひ)
対象の木の樹冠の範囲の全ての場所に施肥する方法です。
庭木への施肥は、対象木の肥料の種類、与える時期や施肥方法などを理解するのはなかなか難しいものですが、樹木は生き物ですから、人間と同じように、酸素や栄養が必要なので、人と同じように大切に扱ってあげてくださいね。
どうしても難しいようなら是非ご用命くださいね。庭木のメンテナンスはこちらから
2024年1月30日更新
執筆者:造園技能士 竜門 健太郎